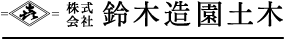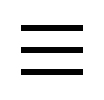お知らせ
お知らせ
藁の仔馬さんから、新年のご挨拶です。
年末の藁ぼっち・門松づくりで余った藁から生まれた
首をふりふり元気な仔馬さんです。
スタッフのSさんが作ってくれました。可愛いでしょう?
今年の干支にちなみ
健やかな始まりへの願いを込めました。
私たちは
冬の風物詩である藁ぼっちや、新年の門松飾りなど
季節とともにある庭仕事を大切にしてきた
昔ながらのお庭屋さんです。
一方で、真剣に、そして楽しみつつ
新しいものや知恵にも目を向けて
日々周囲の風を嗅いでいます。
これからもお客様がふっと心をゆるめ
憩えるお庭をお届けしていきたいと思います。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
一木の美、里山の風景——剪定スタイルのお話
そろそろ12月も中旬なのですが
当社近くの街路樹やお庭の木々の枝先では
黄色や茶色の葉っぱたちが
まだまだ落ちずに頑張っているのが見られます。
やはり年々、落葉の時期が遅くなってきていますね。
大風が吹く日には、青空をふわふわと舞い踊り
なかなか地面に落ちてきません。
まるで、あの夏の暑さを乗り切った葉っぱたちが
最後に思いっきり、空で遊んでいるかのようです。
さて今回は、植木の剪定の形や
様々なお庭の仕立て方について
少しお話ししてみたいと思います。
植木の剪定にはいろいろなスタイルがあります。
例えば、1本1本を単木作りで剪定し
それぞれを名木として、立派なカタチに整えるお庭。
あるいは、空間全体を森や里山の風景として捉え
他の木々たちと馴染ませるように剪定していくお庭。
同じ樹種だとしても、お手入れの仕方は変わります。
ですので、私たちが
お庭の手入れに入らせていただく際には
お客様がそのお庭において
何を大切になさりたいか、どんなお庭にしたいのか、
お話を伺ってから進めるようにしております。
もちろん、1本を格好よく仕立てる為にも
庭師の技術とセンスを磨き続けなければなりません。
一方で、里山のように馴染ませて仕立てる場合は特に
お庭の植木たちそれぞれの性格や
強さ弱さをよく見極めて
お手入れを続けていくことも重要なポイントになるのです。
一つのお庭の中には
強い植物と静かな植物が共存しています。
ですから、育っていくうちにどうしても
優劣がでるものです。
強い子がワアっと伸びてぐんぐん育つ傍ら、
静かな子がじっと我慢して我慢して
そのうちちょっと具合が悪くなってしまっていると
かわいそうですから、
その時は、強い子を多少切らせてもらう…
我慢してる子には、少しゆとりを持たせてあげる…
そんなふうに調整したお手入れをかけています。
樹の種類による そもそもの生命力の違いもあれば
植えられた場所に合う合わないで、加減も変わります。
お庭屋さんとしては
植木たちがどんなふうに育っているか
いつも気にしながら、時には植木に話しかけながら
作業をしております。
お客様からお伺いする、その年の植木たちの様子も
とても参考になります。
いろんな木々やお花がバランスよく共存して
心休まるお庭にできたら、私たちも何よりですから。
お庭の木が「ちょっと疲れてるかも?」と感じたら
いつでもお声がけください。
ご一緒に、お庭の子たちの声に
耳を澄ませていけたらと思います。
画像:公園の銀杏が見事でした。
年末年始休業のお知らせ
平素より弊社をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
年末年始の休業期間について、以下の通りご案内申し上げます。
【年末年始休業期間】
2025年12月31日(水)~2026年1月7日(水)
新年は2026年1月8日(木)より営業を開始いたします。
休業期間中にいただきましたお問い合わせにつきましては
営業再開後、順次対応させていただきます。
本年も多くのお客様に支えられたこと、心より感謝申し上げます。
来年も変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。
画像:先代社長の育てた柿です!
トゲのある木、やさしいお庭 ─ 防犯と暮らしの知恵
今年は夏が長く、急に涼しくなったと思ったら
もう12月がすぐそこです。
年末が近づくと「防犯」の話題が増えてきますね。
今回は、庭木と防犯の関係について
スタッフみんなで、現場での体験を交えながら
話をしてみました。
塀の向こうの「不安」から生まれるご相談
あるお客様のお宅で、最近塀の外にあやしい車が
横付けされ、中を覗き込む男性がいたそうです。
「なんだか物騒だから
塀際にトゲのある植物を植えてほしい」とのご要望が。
お庭でトゲといえば思い浮かぶのは
バラなどでしょうか。
「塀側にバラを植えて誘引し
侵入防止になる植栽にしてほしい」と仰います。
ただ、お庭をお手入れする立場からみると
トゲものはちょっと悩ましい存在です。
お客さまの不安に寄り添いたい気持ちと
実際にお世話する現場の安全との間で
どう折り合いをつけるかいつも課題になります。
トゲもの、痛みの記憶
トゲといえば、思い出話もいろいろです。
スタッフ全員が
アザミのトゲにやられたこともあれば
足袋を貫通するほど
カラタチのトゲを踏み抜いたことも。
一瞬の油断で、鋭い痛みが走る…。
作業現場では笑い話にもなりますが
実際は危険と隣り合わせです。
最近はトゲが危ないという理由で
昔ながらのカラタチを植える家も
少なくなりました。
代わりに、葉先が鋭いユッカランなどを
フェンス側に植えて
防犯に役立てているお宅も見かけます。
トゲのある植物とお客様の物語
ところで、トゲものといっても
防犯だけを目的に
植えられているわけでもありません。
例えば、農家さんのお庭では
サンショウやタラノキなど
季節の味覚を楽しめる木がよく見られます。
また、サルトリイバラ(サンキライ)は
地方によってはお団子を包む葉として使われ
冬には赤い実をリースに飾るなど
昔から暮らしの中で親しまれてきました。
またあるお宅ではウコギが育っていて
「珍しいですね」とお声かけしたら
「植えた覚えがないんです」とのこと。
実生で芽吹いたのでしょうか。
てっきりお客様がお好きで植えて
新芽を天ぷらにして楽しまれているのかと
早とちりして笑った思い出もあります。
こんなふうに、痛いトゲのある植物も
私たちの暮らしの中
様々な形で愛されてきたのでしょう。
お庭屋がトゲと格闘する季節
冬を前に、ユズやレモンの摘果作業が始まります。
これも私たちの仕事のひとつ。
お客様がケガをせず
お庭で実った恵みを楽しめるよう
私たちお庭屋がトゲと格闘しながら実を収穫し
枝を整えるのです。
防犯対策は「トゲ」だけではない
昔、防犯目的でピラカンサを植えてほしいという
ご要望がありました。
ですが、先代社長は
「手入れする身にもなってほしい」と
あえてトゲのない樹種を提案して
お庭を完成させたそうです。
植物で防犯できるのも悪くないのですが
お庭でよろけたり転んだりしたときや
お子さん、ペットが遊ぶときに
ケガのもとになることもあるのです。
そもそも、鉄条網は伸びませんが
植物は伸びます。
防犯のために植えた木も
育てば剪定が必要になります。
だからこそ私たちは
「植物のトゲ」に頼るよりも
侵入経路になりそうな場所を「死角にしない」
お庭づくりの方をおすすめしています。
通行人やご近所から、ほどよく「見える」外構の方が
防犯効果は長続きします。
それに、ちょくちょく植物のお世話をしに
お庭や玄関先に出ているのだって、案外と
ご自宅やご近所を守る効果があるのではないでしょうか。
「庭木と防犯」。
できれば、その植物のトゲ以外の魅力も愛でながら
家族の季節を告げる存在として
お庭で楽しんでいただけたらーー
そんなふうに、願っています。
花壇の土の中に…? コガネムシの幼虫にご用心
今年は9月になっても暑い日が多かったですが
ようやく秋らしい陽気になってきましたね。
夏のお花も、そろそろ終わり。
秋雨の合間、気持ちよく晴れた日には
来たる季節に向けて
お家の花壇やプランターの植え替えを
なさるという方もいらっしゃるでしょう。
花壇を掘り返したり
プランターをひっくり返したりして
土をほぐしている時に
何やらゴロゴロと白い物が出て来ることがあります。
そう、コガネムシの幼虫が
何匹も見つかることがあるんです…。
コガネムシって、どんな虫?
コガネムシの幼虫は、白っぽく太いイモムシで
地中ではCの字状に丸まっていることが多く
掘り出して地面に置くと
腹ばいになってさっさと歩いて逃げます。
7月から9月が産卵時期で
孵化した幼虫は土の中で越冬します。
最近は暑い期間が延び、産卵適期も長くなったのか
その数が増えているような気がします。
幼虫は土の中でひっそりと
植物の根っこをモリモリ食べています。
地中の様子は見えませんから
根の食害にはなかなか気づけないのが困りものです。
ある日突然
植物の元気がなくなってきたり、
プランターの植木に水をやっても
なんだか吸い上げている感じがしなかったり、
あるいは株を持って揺すると
妙にぐらぐらする時などは
植物の根っこの被害を疑ってみましょう。
一方、成虫は緑色のコロンとした虫で
バラや広葉樹の葉っぱを食べます。
夏場に、葉っぱに虫食いの多い樹を揺すると
緑色の成虫がボタボタ落ちてきますので
多すぎる時は捕殺しておきましょう。
コガネムシと似たイモムシの話
土中の白っぽいイモムシで
ハナムグリという虫の幼虫がいます。
彼らは、元気な植物の根っこは食べずに
落ち葉や朽ち木などを食べて
土壌を良くしてくれる益虫の一種です。
見た目はそっくりなのですが
コガネムシと違って腹ばいではなく
ひっくり返って背中で歩くのが特徴。
見つけたらそのままお庭に戻して
土壌改良を頑張ってもらいましょう。
それから、コガネムシの幼虫を
カブトムシやクワガタムシの幼虫と
間違える方もいらっしゃるようです。
カブトやクワガタの幼虫も、ハナムグリと同じで
生きた植物の根っこは食べず
腐葉土や朽木を食べています。
夏の間、自宅のお庭には
カブトやクワガタの成虫がいないのに
腹ばいで歩く白いイモムシが土から出てきたら
残念ながらコガネムシの幼虫の可能性が高そうです。
植え替えシーズンには
土から幼虫が出てきたら
根っこの中にも虫が隠れていることがあるので
根の周りの土をそっとほぐしながら
1匹ずつ取り除きます。
殺虫剤を使うかどうかは
ご家庭やお庭の環境により
ご検討いただくことになりますが
土を掘った時に、物理的に捕殺しておくのも
植物たちの根っこを守るよい方法です。
虫にも虫の事情があって生きていますし
彼らの営みも自然の循環の一つでしょうから
なんでも駆除すれば良いとは思いませんが、
その場所であまりに何かが増えすぎてしまうと
それはそれでバランスがよろしくない気がします。
そして植木たちは
根っこを齧られ続けても痛いと言えず
逃げもできずにそこに居ますので
ちょっとは助けてあげたいなと思うのです。
ちなみに、自然のサイクルの観点からいくと
お庭にくる鳥さんたちが
コガネムシの幼虫を食べていきます。
ムクドリ、シジュウカラ、ハクセキレイ、ウグイス、
季節によってスズメなどですね。
幼虫はプラスチック面を登れません。
植木鉢の下に敷く、プラ製の鉢皿などに載せて
鳥が空から見つけやすい場所や庭の隅っこに
数匹置いておくと、いつのまにか食べていってくれます。
(カップよりもお皿だと、鳥が見つけやすいみたいです)
せっかく育てている植木やお花が
急に弱ったり枯れたりするとびっくりしますよね。
そんな時、病気ではなく虫の影響も考えてみては。
なお、根っこを齧る虫の対策としては
周りに雑草を少し残しておくと
そっちの根っこを食べてくれる場合もあります。
ご自身のお庭に馴染むやり方を
楽しみながら見つけていただければと思っています。
家族と共に育ちゆく庭
先般、20年以上にわたり
お庭のお手入れをさせていただいているお宅で
大掛かりなお庭のリフォームをいたしました。
新築当時は、お子様方がまだ小さくて
お庭で遊ばれることもありましたが
今はもうすっかり成長されました。
そしてお施主様も定年退職されて
ご家族とお庭との関わりも少しずつ変わってきました。
そこで今回は
日々のお手入れが楽になる方向で
一部の植木の入れ替えをしたり、
季節になると果実を楽しめる植物をいれたりと、
「この家で、これから過ごす時間を、どうしたいか?」
この点をご家族と相談しながら
ご希望に沿った新しいお庭を考えたのです。
家族と共に、お庭も育っていいんです
私たちは、個人のお家のお庭は
作りっぱなしではなく
そこに住まうご家族と共に
お庭も成長してよいのではないかと考えております。
もちろんお気に入りのお庭を
ずっと維持できるのも幸せなことですし
それがご自身の生きがいや運動になって
健康維持に役立っている方もいらっしゃいます。
一方で、年を経るごとにお庭の手入れが大変になり
その家に住み続けること自体を難しく感じる方も
いらっしゃるかと思います。
そんなことが気になり始めた時、
これからの人生、我が家でどう過ごしたいか、
どんなお庭だったらよりよい時間が過ごせるか、
立ち止まって考えてみるのもよいかなと思うのです。
家族のお庭ストーリー
もし小さいお子さんがいらっしゃるなら
芝生でゴロゴロできるといいかもしれません。
小さなお花を摘んだり、庭に来る小鳥や虫たちを見たり、
その年齢ならではの楽しみ方があるでしょう。
家族の形は様々です。
例えば、外遊びが好きな動物を飼っている方は
彼らが安全に遊べるお庭にしてもよいかもしれません。
そして子供がだんだん大きくなって
庭で遊ばなくなったら
転んでも痛くない芝生のお庭でなくても
いいかもしれません。
草取りが楽なレンガ敷きのお庭にしたっていいし
お庭の一角に畑を作ったっていいのです。
いずれ子供が巣立った後に
家でゆっくりする時間ができたなら
ここで一度、お庭とのこれからの付き合い方を
考えてみるのもいいですね。
年を取ってから、あまり手のかかる庭だと
時にその家で暮らしにくくなることがあります。
そこで、手間暇はそれほどかけずに
楽しめるお庭に作り替えておけば
住み慣れた自宅で
長く暮らせるように準備ができます。
お庭は、暮らしの中でいちばん身近な自然です。
これからの毎日をどう楽しむか…
お庭がその答えを映してくれるのかもしれません。
戦争と花壇
お花好きのある奥様から、こんなお話を伺いました。
「私が学生の頃、園芸部で
校内に花壇を作ろうとすると
地面を掘れば瓦礫ばかりで
とてもすぐに
お花を植えられるような状況じゃなかったわ」
それが何を意味するのか、すぐには想像できず
私がその状況を思い浮かべるには
ほんの一呼吸、考える時間が必要でした。
奥様の通っていた学校は東京都港区にあり
1945年5月25日の山の手大空襲で
地域一帯が焼き払われた場所にありました。
その方が学校に通われていたのは
戦争が終わって10年ほど経った頃でしたが
それでもまだ、校庭のあちこちに
空襲の瓦礫が埋まったままだったそうです。
「花壇作りは名目で、あれは校庭内の片付け作業
だったのかもしれないわね」
今、私たちがこの近隣でお庭をやろうとするとき
掘ったら瓦礫ばかりということはほとんどありません。
しかし今も、日本国内でも自然災害により
瓦礫の片付けが続いている地域がありますし、
他国では今この瞬間にも戦争が繰り返され
瓦礫の降る中を逃げ続けている方々がいます。
戦後80年の今年、
土を掘り、木を植える、花を育てる…、
そんな穏やかな日々を送れることの尊さを思う、
終戦の日です。
【お水やりのお願い】樹木たちの水が足りていません!
台風が過ぎ、今日も外に出るのが大変な暑さですね。
その台風でも、横浜付近ではそれほど雨が降りませんでした。
今年は雨が少なく、気温の高い日が続いています。
そんな中、お庭の木々や草花の様子が
「なんだかいつもと違う」と感じたことはありませんか?
いま、私たちの身の回りの樹木たちのお水が
全くもって、足りていない状況です。
できれば緊急に、お水やりをしていただければと思っております。
最近私たちがお庭のお仕事をしていると
あちらこちらで樹木が枯れています。
元気そうに見える樹木の葉っぱも、よくみると
通常よりも小さくなってしまっているのです…。
今年の葉っぱが小さい?それ、水不足のサインかも
植物は、乾燥や水不足のストレスを感じると
体を守るために葉のサイズを小さく抑えることがあります。
あるいは、葉っぱの数を少なくすることもあるんです。
これは、葉っぱを小さくしたり減らしたりすることで
葉の裏の気孔から蒸散する水分を減らして
植物たちが水不足に耐えようとしているサインなのです。
しかし、葉っぱの面積が小さくなると光合成しづらく
植物たちの成長エネルギー(糖分)が作れなくなります。
いつもは気孔から水を蒸散させることで
根から上へと水を引き上げているのですが
水が足りないとこの流れが鈍くなってしまいます。
さらに、根っこの活動も鈍って水が上がりにくなると
人間でいえば血の巡りが悪いような状態になり
根から吸い上げている栄養(ミネラル)も行き渡らず
全体の代謝も低下してしまうのです。
これでは、植物たちもどんどん弱って、枯れてしまいますよね…。
お水やりは、朝か夕方がおすすめ!
植物たちは、朝に太陽の光(特に青色光)を浴びると
気孔を開くホルモンの働きが活性化され
そこから気孔を開き、光合成を始め、水を吸い上げます。
ですので植木たちにとっては
朝のお水やりはとても嬉しいものなのです。
そして酷暑の今は、夕方の時間帯もおすすめです!
気温が低くなる時間帯、日差しがないタイミングで
たっぷりとお水やりをしてみてくださいね。
今は各地で水不足のお話も出ていますし
節水が求められる地域では、無理のない範囲で
身近な再利用水をご活用いただけたらと思います。
お風呂の残り湯や、お米の研ぎ汁、
お野菜をゆでたり、レトルト食品を温めるのに使ったお湯なども
活用できます。(もちろん常温にさましてから)
ぜひ、十分にお水やりしてあげてくださいね。
植物たちは、歩いてお水を飲みにいけませんし
黙って植えられた場所で耐えています。
でも、適切にお水をあげ続けていけば
いちど葉っぱが小さくなってしまった植物でも
数ヶ月後に元の葉っぱサイズに戻ることもあるんですよ。
植木はおしゃべりできません。
でも、あなたのお水やりに、きっと応えてくれると思うのです。
夏季休業のお知らせ
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら、弊社では以下の期間を夏季休業とさせていただきます。
休業期間:2025年8月13日(水)〜8月17日(日)
休業中にいただいたお問い合わせにつきましては、8月18日(月)以降に順次対応いたします。ご不便をおかけしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
皆様には素敵な夏休みをお過ごしいただけますよう、心よりお祈りいたしております。
<写真:土壌試験場の畑で取れたスイカです!>
嬉しい一日
「やったぞー!ついに日本一になったぞー!」
と、九州の親父から電話がありました!
昨日は、嬉しいことがたくさんあった一日でした。
これは、ある個人のお客様のお宅で
お庭をつくっている現場での、みんなの様子です。
黙々とブロックをはめる Mさん。
真っ赤な顔でブロックを納めるやいなや
「ブロックを納めたりない!」と勢いよく言ってくる
積極的な Aさん。
無い答えを必死に探しながら庭石を据え
おいらにダメ出しされても、また黙々と石に向き合う Kさん。
まるで「小麦粉の中の飴を探す競技」でもしたかのように
粉だらけになって必死にブロックを加工する Yさん。
スプレッターを使って遠慮がちにブロックを割り
コツコツとハンマーで叩いて納め
レンガ300本を半日で配り終えた YZさん。
「大きな問題点は見つかりませんでした!」と
エアコンの効いた食堂で休んでいるおいらに電話をくれた AMさん。
それぞれが、いいものをつくろうと試行錯誤する。
その背中を見ているだけで、嬉しくなる一日でした。
みんな、本当にありがとう!
…で、九州の親父が言っていた「日本一」というのは、
昨日の福岡県朝倉市が、最高気温全国1位だったそうです(笑)
お騒がせしました!
(画像は、先月九州に帰省した時の写真です。)
【職人の仕事に興味のある方へ】
当社では、庭づくりに情熱を持つ仲間を募集しています。
ご興味のある方はお問い合わせフォームからご連絡を下さい。
- TEL:045-981-3667
- 【受付時間】9:00~18:00(平日)
FAX:045-984-8500