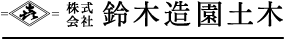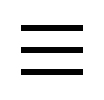お知らせ
お知らせ
菌ちゃん畑に挑戦!新しい土づくりのお話 ④
皆さんのお庭や畑の土って、今どんな状態でしょうか?
土にもいろいろありますよね。
当社の土壌試験場では、野菜たちがぐんぐん育つ
栄養豊かな土を目指して
菌ちゃんたちにお手伝いをしてもらっています。
菌ちゃん畑の土って、どんな土?
土の中には、糸状菌や乳酸菌、酵母菌、
他にも以前リクガメちゃんの記事でご紹介した
植物の成長に欠かせない窒素を土中に取り込んでくれる
根粒菌などの多種多様な菌たちがいて
みんなで上手に補完しあっています。
今回の畑の土づくりでは、糸状菌の働きに注目して
彼らが大好きな 、通気性の良い土壌環境を整えます。
彼らのエサになる枯れ草などの
炭素を多く含む有機物を土にたっぷり混ぜて、
手でさわると軽くてさらさら、ほろほろの土にしてあげると
さらに元気に活動してくれるようになります。
すると、命の役割を終えた有機物たちに向かって
土中から糸状菌たちがするするとのびてきて
ゆっくりと分解を始め
野菜やお花、植物たちが吸収できる栄養素ができます。
虫さんたちと同じく、土中の微生物たちは
土に帰りたいものたちのお手伝いをしてくれるのですね。
これにより栄養たっぷりの土で育つ野菜たちは
病気になりにくく、虫もつきにくくなります。
人間で言えば、栄養状態の良い人は
免疫力が高くて病気になりづらいのと同じことでしょうか。
良いエサになるのは枯れ草、枯れ葉、籾殻、剪定枝。
適度な大きさに割った竹や、古い木。
菌ちゃん畑で育てた野菜の残渣も、土に還せます。
この畑は、私たちの身近にあるものを活用して
土づくりができるのが大きな魅力なんです。
遠くから原材料を買ってこなくても
家庭菜園やお庭で、こうした身近な材料を見つけ
“自給自足”の土づくりに挑戦するのも面白そうです。
日本で使用される化学肥料は
主に国内で製造されていますが
その原材料の多くは海外からの輸入に頼っています。
製造コストの6割が原材料費で、
最近は、中国、マレーシア、カナダなどからの輸入が
主だそうです。(農林水産省「肥料をめぐる情勢」)
そうなると当然、国際情勢や原料価格、運送費の変化、
円安にもかなり影響を受けますよね…。
身近な有機物を活用した土づくりができたら
わざわざ海外から高い値段で
たくさんの材料を買わなくても済むかもしれない。
菌ちゃんたちの活躍を見守りながら
そんな未来を楽しみにしている今日この頃です。
菌ちゃん畑に挑戦!新しい土づくりのお話 ③
私たちの身の回りにあるお庭や公園、畑の土には
それぞれ個性がありまして、
通気性の良い土、湿っぽい土、
酸性土壌や栄養成分の多寡など、さまざまです。
その土に合った植物の種はしっかり育ち
合わなければ育たないし
そもそも芽吹かないこともあるんですよ。
庭師のお仕事をしながら
土と植物の関係で面白いなあと思うのは
先代の社長が折々に言う
「草ってのは、土が呼ぶんだ」ということです。
土が草をよぶって、どういうこと?
例えば、春先に見かけるつくしんぼ。
つくしの根っこはカルシウムやシリカが豊富で
土がカルシウムを欲しがるとあの草を呼ぶのだと言います。
確かに、土が酸性よりで、
カルシウム分等の栄養が不足してくると
スギナ(つくしはスギナの胞子茎)が 元気に出始める傾向があるのです。
他にはヤブガラシなども分かりやすいですね。
水が滞留しているところ、ジメジメしているところに出てきます。
水はけが良くないといけない土壌なのに
滞水してしまっているところにはヤブガラシがでて
根っこをどんどん伸ばし、土中の通気性をよくしてくれます。
土が空気を欲しがってるところにちゃんと生えてくる…
そんな不思議な光景を、度々目にすることがありました。
皆さんのお庭や畑にも、土が呼んでいる草があるかもしれませんね。
物言わぬ土が、ちゃんと必要なものを呼び寄せる、
土、植物、虫、菌ちゃんたちの循環って
本当によくできているなあとつくづく思うのです。
では次回は、菌ちゃんたちの働きについてお話しますね。
(画像:つくしとヤブガラシ)
菌ちゃん畑に挑戦!新しい土づくりのお話 ②
さて、菌ちゃん畑を始めるにあたり
まず取り組むのは「元気な野菜を育てる土づくり」です。
虫に食われないほど元気な野菜を育てるには
土中の微生物たちが元気に生きる畑を目指すのですが
特に「糸状菌」という菌の働きに注目していきます。
みなさんは、草地や森、山など緑の多い場所を
歩いているときに、地面に落ちた枯葉や古い枯れ枝に
白っぽい粉のような、ごく細かい白い糸のようなものが
ついているのを見たことはありませんか?
あれが、糸状菌たちです。
糸状菌は、枯葉や木屑などの
高炭素有機物をゆっくり分解して
土壌中の養分にしてくれたり、
他の菌たちが働きやすい環境を作ったり、
植物の根っこの成長を助けてくれたりしています。
吉田先生は、彼らのことを愛情こめて
「菌ちゃん」と呼んでいるんですよ。
一から畑を作り、畝を立てます。
まず、しばらく何も作物を育てていなかったスペースの
草刈りから始めました。この時に刈り取った草は、
2ヶ月ほど畑の横で野ざらしにしておくと
後で土の中の微生物たちのとても良いエサになるのです。
ススキやチガヤ、イネ科の植物のような
茎が硬い感じの、炭素分が多い枯れ草は大歓迎です。
それからいったん土を均して、水はけ用の溝を掘り、
大人の膝上くらいまである高い畝を立てます。
この高い畝が、菌ちゃん畑の特徴なんです。
一般的な畑の畝はもっと低いのですが、
糸状菌が好む水はけの良い畝を作るには
この「高さ」が必要なのだそうです。
畝を立てた後、雨が降って土が湿ったら
黒マルチという農業用のフィルムシートで全体を覆います。
これで畝の内部の湿度や通気を程よく保ち
菌ちゃんたちがエサを分解してくれるのを待ちます。
2ヶ月くらい待って、土の中に糸状菌の白い菌糸が
見つけられるようになれば、いよいよ植え付けができるのです…。
なかなかの重労働ですが、数人がかりで頑張りました!
畑の周りには囲いを作りました
近隣の畑では、農作業の効率UPのために
多少のお薬は使っていらっしゃることでしょう。
強風の時などにそれらが飛んでくることもありますし
育て始めの菌ちゃんたちへの影響を考えて
新しく作る畑の周りには、木製の囲いを設置しました。
スモーキーブルーの木製フェンスが、いい雰囲気です!
目には見えないし、言葉も発しないけれど
土中で食べ物を待っている菌ちゃんたちのお世話をする…
何だか、日々植木たちと向き合っている
庭師のお仕事にも繋がっているように感じますね。
菌ちゃん畑に挑戦!新しい土づくりのお話 ①
当社では、よりよい庭づくりや土壌環境の改善を
目指して、10年ほど前から土壌試験場を設けて
野菜や花を育てています。
試験場の畑を定点観察するのは
本当に面白く、折々に気付きを得られます。
それは時に
私が先代社長から教えられてきた
日本の庭師の伝統技術や知恵にも結びついており、
何年か越しで「ああ、こういうことか」と
かつての言葉が深く腹落ちする瞬間でもあります。
「菌ちゃん畑」との出会い
畑についてはゼロから勉強するので
いろいろな書籍にも目を通していました。
そんなある日、吉田俊道さんという方が書かれた本で
「土壌中の微生物、特に糸状菌の働きを活用して
元気な野菜を育てよう」という農法が
紹介されているのを読み、がぜん興味が湧いたのです。
というのは、私の畑の白菜は
いつも 外側の葉が虫に沢山食われ、葉脈の繊維だけが残り
まるで綺麗なレースのように見えるほど。
(写真の白菜はまだそこまでではないですが)
家庭菜園などで同じような経験をされた方も
いらっしゃるのではないでしょうか?
あまり薬を撒かずに育てていると
これも仕方ないのかなあと半ば諦めていたのですが、
吉田先生は本の中で
「虫達は弱った植物を食べて、土に帰そうとしているだけ。
虫がやってこない元気いっぱいの野菜を育てればよい」
と仰っていたのです。
植木と野菜がつながった
確かに…!
この考え方、植木にも通じるところがあるのです。
抵抗力が落ちて弱った木には虫がつきやすくなり、
やがて土に還されていきます。
このサイクルは、これまで庭木の管理を通じて
何度も目の当たりにしてきたものでした。
自分の経験と吉田先生の言葉が結びついた瞬間、
「これはぜひうちの畑でも試してみよう!」と
強く思ったのです。
そこで今年の春から、新しいスペースを使って
菌ちゃん畑の土づくりにとりかかりました。
次回は、具体的な畑作り、土づくりのお話です。
冬支度から始まる、お庭との会話
今年も残すところ、1ヶ月少々となりましたね。
庭木が落葉し、冬支度が進むこの時期は
私たち庭師もお庭のお手入れに大忙しです。
ここ2年ほど、気候の変化で 季節の移り変わりが
少しずつずれていると 感じることが増えました。
夏がとても長く、秋冬はぐっと短くなり、
春もまた少し短くなっているように思います。
皆さんも、衣替えのタイミングが変わっていませんか?
そして落葉する時期がずれれば
木の剪定(せんてい)に適する時期も変わります。
剪定は木の健康を保ち
来年も美しい姿で元気に育つために欠かせない作業です。
でも不思議なことに、同じ一つのお庭の中でも
全部の木が同時に剪定タイミングを迎えるわけではなくて…、
どの子もそれぞれに
「私はまだ大丈夫」「そろそろ剪定してほしい」と
都合や個性があるみたいですよ。
ですので、カレンダーだけでなく 木々の様子を直接見て
その都度どんなお手入れをしてあげたらいいかを
ご提案できるよう努めている今日この頃です。
さて、以前から弊社では、土壌試験場の畑を作って
植物たちと気候や土の関係を観察しています。
伝統的な庭師のお仕事、庭づくりは
自然を相手にした知恵の結晶でもあります。
日本の気候や植生に沿い、
人間の近くにあるお庭という場所で
生きとし生けるものが
健やかに生息できる環境を作り育てる。
そのための知見と技術を受け継いでいくことが
とても大切なのではないかと私たちは考えています。
それは、植木を美しく配置したり
見栄えの良い苔や石を並べたりすることよりも
難しいけれど遥かに重要なことで、
いちど庭ができてしまったら目に見えない部分に
思いを馳せる仕事でもあります。
土づくりや土壌改良の研究もその一環です。
私たちの足元にある「土」が
どんな仕組みで 植物達を支え育ててくれているのか、
そして虫や小鳥、植物、土中の菌類まで含めて
全ての生きものたちがどんなふうに循環しているのか、
パッと目に見えなくても大事なこと、
それを識るために、日々地道な観察を続けています。
いろいろ気候変化の激しい昨今ですが…
これからそんな土づくりや畑のお話も
ここに少しずつ書いていきたいと思います。
どうぞお楽しみに!
(秋色の写真を集めました。カラスウリ、ヒメシャラ(橙色)、ハナミズキ(赤)です)
ペットとお庭のやさしい関係
当社が日頃パソコンのことでお世話になっている
Wさんは、リクガメを大切に育てていらっしゃいます。
先日お目にかかった際、写真を見せていただきつつ
普段どんな餌を好んで食べるのかお聞きしました。
すると、リクガメ用の栄養フードなどもあるけれど
小松菜や青梗菜などのお野菜が大好きで
他には野草もよく食べるというお話でした。
そして野菜の種類や栄養バランスを考えるのも
大切なのだそうです。
ただ、そういった葉物野菜も高い時期がありますし
自宅で何かリクガメが好きな植物を
育てられないかと思うことがあるそうで
例えば、桑の葉っぱもよく食べるから
お庭に桑の木を植えたらどうかと 何となく考えているとのことでした。
確かに、カメさんが好きな桑を庭に植えれば
どんどん育って沢山葉っぱが取れるでしょう。
しかし、桑の木はとても成長が早い植物ですし
地植えにすると根も大きく広がるので
他の植物にも影響してしまうなど
後の管理が大変になる可能性があるんです…。
そこで私たちからは
シロツメクサをおすすめしました!
シロツメクサの種は、園芸店やホームセンターで
入手できます。緑肥(りょくひ)とも呼ばれ
農業や園芸での土づくりに役立つ
素晴らしい植物なのです。
根に共生する「根粒菌(こんりゅうきん)」という
微生物を通じて、大気中の窒素を
土壌中に固定する能力があり、
次に植える植物や野菜が元気に育ちますし
化学肥料の使用を減らすのにも役立ちます。
また、根っこが土壌の隙間に入り込むことで
土が柔らかくなり、土壌の排水性や通気性もアップし
後で枯れたシロツメクサを土に鋤き込めば
それもまた良質な土の栄養になるんですよ。
さらには雑草対策にも向いており、
お庭に植えればグラウンドカバーになって
地表を覆い、雑草の繁殖を防ぎ
土壌の養分が奪われるのを抑えてくれます。
ですから、雑草に困っている駐車場などには
シロツメクサを蒔いて育てるのも
草取りの手間が省けてよいと思うのです。
なぜなら、雑草は気になるけれど
シロツメクサが一面に育っていても
背も高くならないし、かわいいし、誰も困りませんからね。
そうそう、もう一つ
リクガメちゃんにとっても嬉しいポイントが。
公園や道端で見かける植物だと
農薬や除草剤が撒かれている可能性もあります。
ご自宅のお庭やプランターで無農薬栽培した
新鮮なシロツメクサなら、Wさんのリクガメちゃんも
喜んで食べてくれるのではと思っています。
お庭を通じて、ペットや自然と心地よく暮らす、
そんなアイデアを形にするお手伝いを
私たち庭師がいたします。
家庭菜園や草対策についても、お気軽にご相談くださいね。
秋の美しい紅葉は、夏の水やりが大切です
街中を歩いていると、あちこちのお庭の紅葉に
心が和む季節になりました。
今年は高温と多湿が長く続いたので
人も植物も さぞ疲労が蓄積していることと思います…。
庭師の私達にとっても
やっと涼しくなり 思い切り動ける季節が訪れたのは
心の底から嬉しいものです。
ただ、今度は日が暮れるのがどんどん早くなり
活動可能な時間が短くなってしまいましたので
ここは毎日テキパキと お仕事を進めるようにしております。
さて先日、あるお客様から
「今年はうちのハナミズキが見事に紅葉しました!」と
嬉しいお知らせがありました。
サムネイルの上の写真は、その木の様子です。
色のグラデーションが目に鮮やかですね。
実はこの木、昨年の秋は殆ど紅葉せず
葉っぱがみんな 茶色く枯れ落ちてしまったのです…。
毎年秋には、リビングや2階から
季節のお庭の彩りを楽しまれていたので
この大切なシンボルツリーのハナミズキが
急に弱ってしまったのかと
みなさんで心配されていたのでした。
今年の初めのお打ち合わせで
「夏の暑い時期に上手に水やりをすると
その後の季節の庭木のダメージを
軽減することができますよ」
とお伝えしたところ、それなら試しに!と
この夏は2〜3日に一度、頑張って早朝に
たっぷりとお水やりをなさったそうで
その成果がこの紅葉に現れたのだと思います。
お手入れ次第で、庭木の様子がこんなに変わるんですね!
紅葉は、日照、水環境、寒暖差の
3つの条件がポイントになります。
そしてハナミズキはとっても水が好きでありながら
根は浅い位置に広がって伸びていく樹木です。
根が浅い樹木は、今年の夏のように
気温が高く雨も降らない日が続くと
水が足りずに葉っぱの先端から枯れていったり
葉っぱからの蒸散を抑えるために
「早期落葉」と言って
通常の落葉期より早く葉を落としてしまうことも
多いのです。
これでは通常のサイクルが賄えず
木はエネルギー切れの状態…。
葉っぱを早めに落としてしまうということは
その分、必要な光合成ができませんから
樹木にとっては
充分にエネルギーを蓄えられなくなって
免疫力の低下にもつながってしまうのです。
街路樹のハナミズキやサクラなど、
早期落葉してしまっている樹木が
残念ながら、今年は街中にたくさん見られます。
夏の疲れが後から出るのは、人も植物も同じなのでしょう。
みなさんのお庭の木は、今年の秋はどんな様子でしょうか。
落葉はしていなくても、 先端が茶色くなっている場合は
「水不足のサイン」です。 落葉した後では
あまりお水を吸い上げませんから、
また来年、新しい葉っぱが出てきた折には
夏の間もどうぞたっぷりめに
お水をあげてやってくださいね。
下の写真は、モミジバフウの紅葉です。
イガイガの形が可愛い実がたくさんついていました。
散歩の折には、そんな街中の木の実との出会いも
ぜひ 楽しんでいただけたらと思います。
ここ2年くらいの酷暑に植木屋さんが思うこと
最高気温、概ね20度台が続くようになりましたね。
植木たちや苗たちも漸く一息ついているみたいです。
さて、ここ2年くらい本当に夏が厳しくて
私たちの身の回り、お庭の木々達の生育状況が
かなり変わってきたように思います。
気温も高く、陽射しがあまりにも強い為でしょうか。
例えば、お庭のシンボルツリーとして
椿を植えることがよくありますが、
最近はこの椿が暑すぎて枯れてしまう、
今までは問題がなかったのに、陽射しが強すぎて
徐々に元気がなくなり新芽を出さなくなってしまう…
そんなケースが、地元でも何件か見受けられるのです。
最初にお庭を設計する時は、
その場所の風通しや日当たりなどを観察し
どんな土なのかをチェックして
その場所で元気に育ちそうな植物を選びます。
今後はさらに、年間数ヶ月に及ぶ酷暑の影響も考えて
お庭を作っていかなければならないのかもしれませんね。
今、元気がなくなっている木には支えをしたり
栄養をあげたりして、あとはその子の生命力を信じ
回復できるか見守っていきます。
そして実は、畑の作物にも同じような話があって…。
夏の間、暑すぎて種を蒔いても
全然芽吹かない時期がありました。
例えば当社の土壌試験場の畑にニンジンの種を蒔いても
種たちがバテてしまうのか
うんともすんとも芽を出さなかったのです…。
そこで、詳しい方に教えていただいて
ニンジンを撒いた場所に
写真のような白いネットをかけ
日差しを少し調節してみました。
こちらは農業用の遮光シート(ネット)というもので
最近は園芸品店などでも入手できます。
黒っぽい土は、太陽の光をたっぷり吸収するので
そのままだと土中の温度が
30度を悠に超えて温まってしまいますから、
この白いネットで光を反射させようという作戦です。
しばらくすると、土の中の温度が少し下がったようで
見事にニンジン達が芽吹いてくれました!
(雑草の種もいっぱい芽吹いてしまいましたが…)
あんな小さな種達も
自分たちが上手く育っていける環境を
周りの温度などから見極めている…
自然の仕組みは、本当によくできていますよね。
(写真のかわいい新芽は、ほぼ同じ時期に
当社の育苗小屋内で、土の温度が上がりすぎないよう
育てていたリーフレタスグリーンです。
ポイントは土の温度みたいですね。)
漁業の方でも、ここ2年くらいの
水温上昇の影響で、取れる魚の種類や漁獲量が
相当変わったという報道もあり…
陸も海も、地球のあちこちで
何か様子が変わってきたのかなと思いつつ
今日もお手入れする植物たちに
「調子はどうだい?」って心の中でそっと声をかける
植木屋さんなのでした。
カミキリムシのお話
お彼岸を過ぎ、真夏よりは過ごしやすくなりましたが
まだ時折蒸し暑い日もあって
本格的な秋まではもう少しですね。
今のように程よくあたたかい時期というのは
虫さんたちにとっても活動しやすい時期なので
お庭のお手入れの際には
樹木の生育に影響を及ぼす虫さんが増えていないか
気をつけてチェックするようにしています。
先日も、マンションのお庭の手入れをしていた時に
樹木に穴をあけてしまうカミキリムシの
フラス痕を見つけました。
フラスとは
幼虫が木を食べた時に出す木屑のことです。
虫の種類によって、木屑っぽいもの、粉っぽいもの、
蜂蜜状のものなど、
いろんなタイプのフラスがあるんですよ。
今回見つけたのは、ホシベニカミキリという
赤い背中に水玉模様という、なかなかオシャレ?な
カミキリムシのフラス痕でした。
樹の幹に穴が空いていて、
そこからオレンジ色っぽい何かが
こぼれ出ている感じで、お庭ではっと目を引きます。
(その場に成虫はいませんでしたが
他の現場で撮った
ホシベニ成虫の写真も載せておきますね)
このまま木の内部をどんどん食われてしまうと
木の構造を弱めてしまい、木が倒れやすくなるなど
問題を引き起こすこともあるので
可哀想ですが、殺虫スプレーの注入処理を
させてもらったのでした。
カミキリムシが樹木に穴をあける理由は
主に産卵や幼虫の生育のためです。
メスのカミキリムシは、産卵時に樹皮に穴をあけ
その中に卵を産み付けます。
孵化した幼虫は、木の内部を食べながら成長し
これが結果的に木の健康に影響を与えることになります。
自然界において、カミキリムシたちは
弱った木や倒木を食べ、土に返してくれるという
大切な役割を果たしてくれているのですが、
私たち人間のお庭の木々や農家の果樹などを
たくさん食べられてしまうと困るので
時にはこうして対処をしなければなりません…。
最近は、特定外来生物のカミキリムシの
被害が増えており、各自治体で警鐘を鳴らしています。
「東京都 カミキリムシ」
「神奈川県 カミキリムシ」など
お住まいの自治体名とカミキリムシ、と入力して
ネット検索すると
様々な対処情報が出ていますので、
気になる方は一度調べてみてくださいね。
さて余談ですが…
巷ではカミキリムシのガチャ
(1回1000円の完全マニア向け)があるようですね。
私もやってみたくて探しているのですが
なかなか巡り会えないのです。
実際の成虫やフラスには出会えているのに…
この ガチャポンは見つけられていないものの、
生物学を専門にされている福岡伸一博士の
エッセイ本「ルリボシカミキリの青」を
最近注文したところですので、
来たる読書の秋には
是非ともこちらを楽しもうと思っています。
秋のお彼岸、おはぎの話
この連休は、秋のお彼岸で
お墓参りをなさる方もいらっしゃるかと思います。
真夏のお盆時期よりは気温も下がりましたが
外はまだ蒸し暑いので
どうぞ気をつけてお出かけくださいね。
さて、お寺さんにはお庭があり
そのお墓には植栽もありますので、
私たち植木屋さんが時々お手入れに伺います。
例えばお盆前の時期などは、墓地は日陰も少ないので
ものすごく暑くて、大変な作業になります…。
でも、お墓の周りの植木をさっぱりきれいにすると
そこに眠るご先祖さまたちも
きっと喜んでくださるからと
自らに言い聞かせて頑張っております。
先日、お墓参りに行った際には
お墓の近くの植木周りの土が乾いていたので
「お前も暑い中、頑張ってるなあ」と声をかけて
水桶のお水をあげました。
何だか他人事とは思えませんでしたのでね…
お彼岸のお菓子といえば、おはぎですね。
邪気を払ってくれる力があるとされる小豆と
五穀豊穣を祈念する餅米で作るお菓子を
春と秋で「おはぎ」「ぼたもち」と呼び分けています。
秋の「おはぎ」は、まさに萩の時期なので
花の形に見立てて、少し細長い形に丸めます。
(写真のピンクのお花が、萩です)
春の「牡丹餅」は、季節の牡丹の花になぞらえて
まんまるく作るのです。
さらには、餡子にも違いがありまして…
農家さんに伺ったお話では、
小豆が収穫される秋には、柔らかくて香りの良い
豆の皮の風味を楽しめる粒あんを。
そして春まで貯蔵された小豆は
皮が固くなってしまうので、今度はこし餡で。
同じ小豆でも、時期によってこんなふうに
味わい方を変えているのは面白いですね。
今では年中どちらもいただけますが
植木と季節にちなんだ、素敵なお菓子の一つです。
- TEL:045-981-3667
- 【受付時間】9:00~18:00(平日)
FAX:045-984-8500